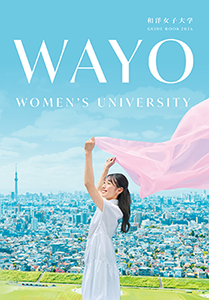人文学部
こども発達学科
乳幼児期に焦点をあて、子どもの
保育・幼児教育の理解を深め実践力を高める
少子化と子育てへの不安感、児童虐待問題、発達障害、保育制度改革……子どもの成長・発達に関するさまざまな問題に、
社会的な関心が高まっています。現代の子どもを取りまく問題に、専門家として対応できる知識と技術を身につけた人材を育成するのが、
こども発達学科です。乳幼児期に焦点をあて、子どもの保育や教育の理論と、現場で活躍するための実践力をバランスよく学びます。
所定の科目を履修することで、「幼稚園教諭一種免許状」と「保育士」の資格を取得できます。
保育について徹底して学び、幼児教育や保育の専門家として活躍しませんか。
こども発達学科の学びや保育者の待遇改善を紹介する、特設サイトを公開中!
動画で見るこども発達学科
こども発達学科の学科説明や施設紹介の動画はこちらからご覧頂けます。
こども発達学科の学び

保育・幼児教育の理解を深め、
実践力と専門性を身につける
幼稚園教諭一種免許状と保育士資格の取得をめざし、質の高い保育のための教養と実践力を養成します。人に対する優しさや心遣い、高い専門性と教養、自ら考え行動する力を育てるため、グループで作り上げる授業や、少人数のゼミ形式の授業を数多く用意。もちろん、実際の保育の場での実習も豊富に展開します。こどもの教育と発達について、きめ細かく学べるカリキュラム構成です。
将来像~卒業生の活躍
こども発達学科で学んで、社会で活躍している先輩たちを紹介します。
※記事はすべて取材当時のものです
FOUR YEARS OF LEARNING
4年間の学び
大学4年間でどんなことが学べるの?こども発達学科で学ぶ内容をご紹介。
保育に関する基礎理論を学ぶ
大学での学びの基礎とともに、「保育原理」「保育の心理学」「保育学入門」など、保育に関する基本的な理論や知識を学びます。保育とは何か、保育者の役割、保育の歴史などについて理解するとともに、子どもの心理や発達についての根幹となる知識をしっかりと身につけ、2 年次以降の学びのための基礎固めをします。
保育の現場を知り、知識と結びつける
保育の記録、計画から実践・評価に至る流れを理解し、実践の第一歩として幼稚園での観察実習を体験します。授業では「保育内容総論」「保育課程・保育の計画論」などを学び、生活習慣や心身の発達、食事・睡眠・運動の持つ意味、遊びの意義といった、子どもの生活を取りまくさまざまな分野についての知識を深めます。
実習・演習を通じて実践力を高める
これまでの学びを基礎に実習を通じて子どもや保育についての理解を深めます。「こども発達学ゼミ」など少人数の演習を通じて、理論と実践を結びつけ、保育の現代的課題に向きあいながら、保育者としての実践力を高めます。
保育現場での応用力と、視野を広げる
「こどもの理解と援助」「保育・教育実践演習」などの授業で、子どもの発達を支援する意味と意義をしっかりと理解。4年間の学びの集大成として、卒業研究にも取り組みます。
将来像
幼稚園教諭や保育士のほか、音楽教室、子ども服や玩具など子ども関連の企業で、
保育学をはじめとする知識と技術を活かして活躍することが可能です。
LEARNING POINT
学びのポイント
多彩な演習や早期からのキャリア教育。学科の学びのポイントをご紹介。
少人数制の授業で深く学べる
学生一人ひとりの顔が見える少人数制。演習など学生が主体的に取り組む科目では1クラス35名程度にクラスを分割し、授業を実施します。特に3・4年次の「こども発達学ゼミ」では、7~8名のグループで、各自の関心に合わせた学習を行います。
地域の施設と連携した実践的な学び
学内の授業だけでなく、幼稚園や保育所、子育て支援機関などの施設での課外学習も実施。地域社会と関わりながら、実践的に学ぶ機会が豊富。少人数制を生かし、異なる授業同士の連携や、学年の垣根を越えた学生の交流もさかんに行われています。
学生と実習先をつなぐ、きめ細かなサポート
きめ細かな実習サポートもこども発達学科の特長です。将来の進路を見据えた実習先の選択がきるよう個人面談でアドバイスを行ったり、日頃の学生の様子をよく知る教員が実習先を訪問したりするなど、手厚い支援を行っています。
早期からのキャリア教育で将来像を具体的に
卒業後の仕事をイメージできるよう1年次からキャリア志向を育成。キャリアを意識しながら実習を体験することで将来像を具体的に描けます。就職率は100%で、卒業生は公私立の幼稚園や保育所の現場を中心に様々な分野で活躍しています。
CLASS INTRODUCTION
ピックアップ!授業紹介
地域の子どもたちを大学に招いての実習の授業など、和洋ならではの授業をご紹介。
地域との強力な連携による実践的な学び

大学の施設に地域の子どもたちを招待するなど、地域の保育の場に出る活動を定期的に実施。学生たちは、子どもたちと一緒に遊ぶ中で、子どもと関わるための応用力を伸ばしています。また、大学に保護者を招いて子育てについて話をきくなど、大学の近隣地域にある子育て広場や子育て支援センターとの連携も強化。子育て支援の現状を理解するとともに、保護者の方々が抱える悩みや課題の解決にも積極的に取り組んでいます。このような活動を通じて学生は、子どもたちだけでなく保護者への対応を含めた実践力を身につけています。
PICK UP 科目
保育学入門
保育の歴史と現状を踏まえながら保育とは何かを学びます。子どもの発達や子どもと保護者を取り巻く環境の変化を知り、子ども理解に立った子ども観を確立するとともに、子どもの行動に共感し、保育を共に楽しむ力を身につけます。
こどもと音楽Ⅰ
グループ授業と個人レッスンを通して、子どもの未分化な表現を支えるための、基礎的な音楽知識、技術の習得をめざします。個人レッスンでは、個々のレベルに応じたレッスンを行います。
こどもと造形
「こどもと表現」での学びを踏まえ、造形表現活動を実施する際に必要な知識・技能を深めます。また、制作と鑑賞を通して造形表現の面白さを知り、学生自身の豊かな感性と創造性を高め、保育の場で工夫する力を身につけます。
こどもと言葉
人間の言葉が果たす機能や意義、子どもが人やものなどの環境と主体的に出会い、言葉の世界を豊かに繰り広げていく発達過程や子どもにとっての言葉の意味を考えます。
幼稚園実習Ⅱの指導
実習の目標を定め、学級や子どもの実態に即した指導計画立案、教材準備を行う実践力を身につけます。事後指導では、面談、自己評価、事後レポート等で振り返りを行い、学びの定着をはかります。
乳児保育
3歳未満児の発育・発達を踏まえ、乳児保育の意義や目的、内容、環境について学びます。また、こども発達学科が所有する豊富な教材を使って、沐浴、授乳、離乳食の援助など確かな知識と実践力を身につけます。
こどもと健康
子どもの健康な心と体を育む視点から、遊びの意義、運動発達、動きの獲得、運動経験の在り方について学ぶ科目です。運動遊びを体験しながら、運動技術や安全配慮、指導計画など保育を実践する力を身につけます。
こどもと環境
子どもの遊びを実際に体験しながら学ぶ1年次前期の科目です。子どもが自然に対してどのように興味・関心をもっていくのか、子どもが自然とかかわる意味を理解し、保育者としての知識や感性を育みます。
GRADUATION THESES AND PROJECTS
卒業論文・卒業制作
大学4年間で学んだ集大成。卒業論文・卒業制作の取り組みをご紹介。
4年次には、4年間の集大成として、専門の教員から指導を受けながら、卒業研究に取り組みます。
ここでは卒業論文のテーマの一部をご紹介します。
卒業論文タイトル例
1. 令和2(2020)年度
- 離乳期の食事援助の分析
- 多文化社会における保育実践の課題ー多文化共生保育の実現に向けてー
- 女子大学生における新しい生活様式下のスポーツ頻度とメンタルヘルスの関連
- 保育室内の環境と再構成に関する保育者の意図や願いについて
- なぜごっこ遊びが子どもたちに好まれているのかー子どもにとってのごっこ遊びの魅力とはー
- 子ども食堂の運営の現状と課題に関する研究―運営スタッフへのインタビュー調査からの考察―
- 製作場面における子どもの主体性を考える一斉活動場面と自由遊び場面を比較してー
- 1・2歳児の反抗・自己主張に対する保護者の感情および対応
- 気になる子どもとその保護者の特徴、保育・家庭養育における困り感の比較―気になる子どもの家庭支援―
- 子どもの音楽的活動における保育者の役割とポテンシャルの関係―モンテッソーリ教育での音楽的活動の映像分析を通して―
- 自然環境を用いた保育教材の開発・提案ー太陽光を生かしたセルシアター
2. 令和元(2019)年度
- 実写版「美女と野獣」のベルを支える人物の行動分析
- 育児をする養育者の心理的な特徴と保育支援
- 発達障害の子どもの保育的な支援
- 幼児と大人で感じるおもしろさは違うのか ―アニメーション「妖怪ウォッチ」を題材に―
- 清潔に関する絵本の実態―どのような内容がどのくらい存在しているか?―
- 保護者はどのような視点で玩具を選考するか
- 音楽の嗜好性と映像との関係
- 子どもの歌の仕組みと惹きつける魅力
- 子どもの生きづらさに関する研究-児童養護施設で暮らす子どもへの偏見・差別に着目して-
- 砂場とその周辺にあるモノとヒトの関わりについて―動き・道具に着目して―
- 保育者は環境構成をどのようにして意図しているのか
- 育児に対する社会の偏見 ―母親像・父親像の変容―
- つどいの広場を利用する母親の育児ストレスとニーズ
- 祖父母の子育てへのかかわり ―祖父母世代・子育て世代からみる"孫育て"―
3. 平成28(2016)年度
- 遊びの中で育まれる子ども同士の人間関係 ―他児の遊びを模倣することを通じて―
- 子育て支援における音楽活動によって育まれるもの
- 幼稚園、保育所における遊びを豊かにする環境
- 子ども虐待対応における保育所の役割に関する研究
- 保育学生の実習段階による子どもへの対応の違い ―いざこざ場面のアンケート調査から―
- 児童養護施設におけるペアレンティングへの保育活動の貢献
- 戸外遊びが幼児の体力・運動能力に及ぼす影響
- 『講談社の絵本』に見る戦時下の絵本
- 自閉症スペクトラム障害の幼児のこだわり行動に着目した保育について
- 植物を使用した造形活動について
- 保育園における幼児の運動遊びの実態と課題 ―戸外あそびに注目して―
- 聴覚障害児をもつ家族、きょうだいへの支援について
- 母乳育児の支援の違い ―家庭と集団保育―
- レオ・レオニの絵本について
- 5歳児はどのように仲間と遊びを共有するか ―視線行動に着目して―
- 音楽と記憶の関連性の研究 ―音楽は記憶をどのように想起させるのか―
- 育ち合うクラスづくりのための保育者の役割
- 乳児に対する保育者の働きかけ ―言葉かけの分析―
- 幼小接続の意義と接続における課題に関する研究
- 子育て支援施設からの「情報」発信に関する研究
卒業制作タイトル例
1. 令和元(2019)年度
- 0歳児を対象とした布素材の教材開発
- ブラックライトを用いたあそびの開発
- 眼球の動きを促す玩具の開発 ―視覚障害を持つ幼児を対象に―
QUESTIONS AND ANSWERS
学科Q&A
学科に関するよくあるご質問。
-
幼稚園教諭免許の一種と二種の違いを教えてください。
-
幼稚園教諭一種免許状は4年制大学で、二種免許状は短大や専門学校で取得できる資格です。就職後の業務内容に違いはありませんが、幼稚園によっては一種免許状取得者の方が給与面などで優遇されることもあります。
-
実習は4年間で、どれくらいありますか?
-
実習は2年次から始まります。幼稚園教諭をめざす場合、2回(合計4週間)の実習、保育士をめざす場合、保育所・保育所以外の児童福祉施設をあわせて3回(合計6週間)の実習があります。合計5回の実習を行います。
-
ピアノはどの程度できていたらよいですか?
-
まったくの初心者でも個人レッスンや日々の自己練習の積み重ねによって、子どもたちの遊びや歌に合わせて弾けるようになることを目標としています。個人レッスンはそれぞれのレベルに沿って学ぶことができます。 しかし、入学前に準備可能なら、前もって準備しておくことをおすすめします。