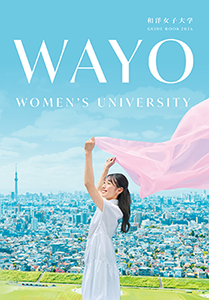人文学部
心理学科
人の心を支える知識と技術を学び、
思いやりと自立心を兼ね備えた女性をめざす
あなたは、人の心の不思議について、感じたことや考えたことはありますか?
心理学科では、心理学を体験や実践的な実習を通じて理解することができる授業やゼミを多数用意しています。
心理学の専門性を身につけ、自分に誇りを持つとともに、社会の中で人と人とのつながりを大切にできる、
思いやりと自立心を兼ね備えた女性を育成するのが目標です。
心理学の専門家をめざし、大学院に進学する人のための専門科目も開講しています。
心理学科で、人の心を支える知識と技術を学んでみませんか。
心理学科の受験を検討している皆さんへ
学科ニュース
動画で見る心理学科
心理学科の学科説明や施設紹介の動画はこちらからご覧頂けます。
心理学科の学び

「心」のありようを学び、
人の心を支える知識と技術を
身につける
人々の心の育ち(発達)や心を豊かに育てる教育のあり方、癒しなど、心のありようを学びます。心理学の基礎から専門科目まで、体験型の学習を多く取り入れながら、学生自身が「できる」「わかる」を体感できる教育を展開しています。認定心理士やピアヘルパーなどの資格取得も手厚く支援します。また、2019年度より公認心理師資格取得のためのカリキュラムも備えました。現代社会の抱える問題に向き合い、心の問題の解決に取り組める、人を支える知識と技術を持った女性を育成します。
将来像~卒業生の活躍
心理学科で学んで、社会で活躍している先輩たちを紹介します。
※記事はすべて取材当時のものです
FOUR YEARS OF LEARNING
4年間の学び
心理学科の4年間のカリキュラムをご案内します。
心理学に親しみ、ベースとなる知識を身につける
「心理学新入生セミナー」や「心理学概論Ⅰ・Ⅱ」「臨床心理学概論」「心理学統計法」などの科目を通じて心理学に親しみ、専門知識のベースとなる考え方を学びます。また、社会・集団・家族心理学(社会・集団)、司法・犯罪心理学、ストレス心理学、メディア心理学も学びながら、大学全体で開講されている多彩な共通科目を学ぶことで、人の心を取り巻く文化や社会、自然環境を知りましょう。そして、語学やパソコンのスキルを身につけるのもこの時期です。
演習や実習で心理学を体感する
専門課程への導入として、「心理学基礎演習A・B」や「心理統計処理演習」など、体験を重視した演習・実習科目に取り組みます。さらに「学習・言語心理学」「教育・学校心理学(教育)」などの専門講義科目も学びます。
心理学の具体的な技法を体得する
心理学の方法論を実際に体得する「心理学実験」に取り組みます。事後指導の時間も設定し、学生一人ひとりを丁寧に指導します。「心理学演習Ⅰ・Ⅱ」では興味あるテーマについての発表やディスカッションを行い、心理学への理解を深めます。さらに、「障害者・障害児心理学」「心理学研究法」などの専門科目を学びます。また、公認心理師を目指す方は、「臨床心理演習(心理演習)」「臨床心理実習Ⅰ(心理実習)」などの科目で、臨床心理学に関する実践的な技法を体得します。
学びの総まとめと「卒業研究」
3年次までに培われた基礎知識と技能をもとに、興味や関心に応じた卒業研究に取り組み、大学での学びの総まとめを行います。さらに深く学びたい人、大学院進学をめざす人に向けた「心理学問題演習Ⅱ」などの専門性の高い授業も選択できます。
将来像
企業の人事部門や営業部門などのコミュニケーション能力が重要視される仕事や、
消費者心理のデータ分析を必要とするマーケティング部門などで、
心理学科で学んだ専門知識を活かして活躍できます。
また、医療、教育、福祉等の分野でカウンセラーとして働くための土台を作ります。
LEARNING POINT
学びのポイント
幅広い領域から心理学を学ぶ。学科の学びのポイントをご紹介。
複雑な心の構造や動きを学ぶカリキュラム
発達、臨床、教育、学習、社会、産業にわたる心理学の幅広い分野を網羅したカリキュラム構成が心理学科の特長です。人間の心の複雑な構造や動きにアプローチするべく、様々な領域から心理学を学んでいきます。
心理学の知識と技術を学び、認定心理士の資格を取得
人間関係の悩みを抱える人が増えたといわれる現代社会においては、心理学に基づいた問題解決能力を身につけた人材が求められています。心理学科では、所定の科目を修得することで「認定心理士」の資格を取得することができます。
大学院進学も視野に入れたカリキュラムを用意
心理学をより専門的に学びたい人、カウンセラーなど心理学の専門家をめざす人のために、大学院への進学も視野に入れたカリキュラムを用意しています。大学院で知識を深めることで、「臨床心理士」や「公認心理師」資格取得への道を拓くことができます。
大学院受験サポート
和洋女子大学には心理学分野の大学院はありませんが、大学の大学院への進学をサポートする科目(心理学文献購読、心理学問題演習Ⅰ、心理学問題演習Ⅱ)を設けています。詳細はこちらから
心理学を学ぶことで自分を客観的に見つめる
「自分とは何者なのか」「自分はこれからどうなっていくのか」。それらを客観的に見つめる視点は、社会の中で自分を見失わずに生きていくために必要です。そうした人生に対する問いを解明するツールとしても、心理学は役立ちます。
CLASS INTRODUCTION
ピックアップ!授業紹介
発達心理学や臨床心理学など、日常生活でも役立つ授業をご紹介。
実習や体験が豊富なカリキュラム

本当の意味で人々の心の内実に迫る、「生きた心理学」を学べるのが心理学科の特長。そのため、実習や体験を豊富に取り入れたカリキュラムを用意しています。
PICK UP 科目
臨床心理学概論
臨床心理学とは、悩みや不安、困難さを抱えている方の状態を理解し、心理学の知識や技法を用いて支援や援助を行うための学問です。講義では、心理テストやカウンセリングの手法などの基礎的な知識を身につけます。
司法・犯罪心理学
刑法や少年法、児童虐待防止法などについて知り、刑務所、少年院、児童相談所などの機関の概要を学びます。また法務教官、家庭裁判所調査官、児童心理司など、心理学の知見に基づく活動と活動倫理について学びます。
青年心理学
自分自身のこれまでの人生を振り返り、これからの生き方を模索する時期である「青年期」。青年期の変化への着目、青年の問題への理解、青年の生き方の模索などを通して、青年の心理を学びます。
心理学実験
人間の発達を科学的な根拠に基づいて理解するために必要な、調査や実験の専門的な技法を実習し、データの収集や処理の基本的な手法、レポートの作成方法を具体的に学びます。
コミュニケーション心理学
人の表情や言語の使い方などから、相手の感情や心の様子を読み解くことを学び、コミュニケーションの成り立ちを再度、検証します。
発達心理学
誕生から死に至るまで、人は発達を続ける生き物です。この授業では、遺伝や環境の制約を受けながらも人間が主体的に人生を形成していく過程を学びます。誰もが持っている発達の可能性を実現していく方法を一緒に考えていきます。
メディア心理学
私たちは日々、様々なメディアに接し、他者とコミュニケーションをしたり、様々な情報を得たりしています。この授業では、身近なテレビなどのマスメディア、電話やメールなどのモバイルコミュニケーション、インターネットを用いたソーシャルメディアなどを取り上げ、各特徴や人に与える影響などについて心理学的視点から取り上げます。
GRADUATION THESES AND PROJECTS
卒業論文・卒業制作
大学4年間で学んだ集大成。卒業論文・卒業制作の取り組みをご紹介。
4年次には、4年間の集大成として、専門の教員から指導を受けながら、卒業論文に取り組みます。
ここでは卒業論文のタイトルの一部をご紹介します。
令和5(2023)年度 卒業論文タイトル例
- ダンスが与えるイメージについて〜雰囲気の異なるジャズダンスが与えるイメージの違い〜
- 女子大学生の失敗に対する価値観と精神的健康との関連
- 女子大学生における日常生活での香りに対する意識と自意識との関係
- 絵画鑑賞における癒し評価基準の分析
- 大学生における課題の先延ばしに関連する認知行動的要因の検討
- 「可愛い」や「美しい」といった言葉の相補性が与える影響について~美容意識や美容実態の検討~
- 大学生のネット依存傾向に関する研究〜実態と対策に焦点を当てて〜
- 女子大学生の多様性の捉え方について~自己意識と自分らしさへの考え方に着目して~
- 完全主義傾向から捉える推し活―精神的健康との関連―
- SNSのアカウントを複数持つ人の性格特性の検討
- 女子大学生における目標達成までの困難と認知の関連
- 大学生におけるHSP傾向が自己認知に及ぼす影響について
- 女子大学生による自己愛的脆弱性と対人依存欲求、共感性の関連性の検討
- 女子大学生におけるLGBTに対する受容感とカミングアウトの関係
- インディーズアーティストのファン心理について
- 女子大学生の音楽聴取による気分変化と自尊感情の関係
- 女子大学生の日常生活が精神状態に及ぼす影響について
- 名前の音の響きと性格の関連性ー名前の最後の母音が性格に及ぼす影響についてー
- 大学生におけるスポーツでの試合前の不安に対する対処法
- 女子大学生における“ながら視聴”の実態とネット依存の関連
- 完全主義認知およびアクセプタンス傾向の程度がストレス状況下における不快情動およびタスクパフォーマンスに及ぼす影響
令和4(2022)年度 卒業論文タイトル例
- 女子大学生の友人関係における山アラシ・ジレンマと自尊心の関連
- 女子大学生における自己開示と心理的幸福感の関係
- 関西アイドルの魅力について~関西弁の楽曲によるイメージの変化~
- 恋人および推しの存在と自分磨き行動との関連
- 女子大学生の性格特性と魅力を感じる雰囲気の関連について
- 泣くことによる心理的変化と性格特性との関係性に関する研究
- インスタグラムに投稿された写真に対する評価
- 女子大学生の結婚観とキャリア志向性の関係
- 音楽の歌詞・メロディが感情に与える影響
- 商品パッケージが消費者の消費行動へ与える影響について―化粧品に注目して―
- 女子大学生における仮想的有能感と自己開示の関連および潜在的いじめ関係者との関連
- 乗り物の座席選択とパーソナリティの関連について
- 女子大学生における先延ばし行動の繰り返しに関連する要因の検討
- 女子大学生の身体装飾意識と自尊感情との関連性~ピアス・ヘアカラーが及ぼす内外的意識はどう変化するのか~
- 香水に対するイメージと人物の印象形成の関連
- 子どもの頃の経験が現在の恋人関係にどのように影響するか
- コロナ禍におけるアルバイト環境の変化と罰感受性の程度が精神的健康に及ぼす影響
- アイドルを応援することが主観的幸福感とストレスに及ぼす影響
- 親子関係の親密さが心理的自立に及ぼす影響について
- 化粧をする時としない時の感情の違いに関する検討
- 女子大学生の対面とSNSの友人関係と生活充実度の関係
令和3(2021)年度以前の卒業論文タイトル例はこちらから(クリックしてご覧ください)
令和3(2021)年度 卒業論文タイトル例
1. 自己意識の心理学
自分への意識や態度、性格など、自分のことだからこそ見えにくい心を探求しています。
- 期待されていない場所で歌うことの背景要因について
- 嫉妬と羨望から見る自己顕示欲との関係性
- タオルケットが与える不安軽減について-青年期まで残存する移行対象-
- 自己肯定感が恋愛における蛙化現象に及ぼす影響と性差について
- 家族構成が抑うつと自尊感情に与える影響について
- 「ひとり反省会」の実態調査
- 女子大学生の場の環境による口数の量について
- 女子大学生におけるダイエット行動と自己肯定感の関係
- 女子大学生の健康状態と主観的幸福感の関連に関する研究
- 言霊が行動や感情に与える影響について
- 自己の二面性の自覚と矛盾した行動の関連
- 懐かしさに対する態度と性格の関連
- 女子大生におけるダイエット行動にYouTubeが及ぼす影響について
2. 対人関係の心理学
家族関係、友人関係、恋愛と結婚など、人と共に生きる私たちの心を明らかにします。
- 恋愛が私生活に与える影響について
- SNSで知り合った人とリアルで出会う人との人間関係
- サークル内の対人関係に関する調査
- 対人関係における意外性の影響について
- 女子大学生の友人満足感と対人ストレスコーピングの関係
- 母親と娘の信頼関係について
3. 生活と文化の心理学
SNS、映画、小説、音楽、アニメなど、身近な生活と文化に表れる心の意味を分析しています。
- ファン行動と主観的幸福感の関連について―恋愛と認知度に着目して―
- 色に対して抱くイメージと楽観性の関連について
- メンズメイクの大学生への浸透性について
- エンターテインメントが女子大学生に与える影響
- 音楽から受ける感覚の検討
- ファン対象に対する感情がメンバーカラー・グループ(チーム)のイメージカラーの取り入れ方にどのように影響するのか
- 色が性格に与える心理的影響-人のイメージとの関連から-
- 被服の色が着用者に及ぼす影響について
- 目に対する意識の検討-化粧と美容整形の観点から-
- 性格とSNSの利用状況からみる友人関係の築き方
- マスクの色が他者に与える印象について
- コンサート参加における同行者による幸福度の検討
- 女子大学生のピアスを中心とした身体装飾の許容範囲についての検討
- バーチャルタレントに対するファン心理の特徴
- 『鬼滅の刃』の人気の理由とは-悲劇作品の観点からの検討-
- アイドルが女性に与える影響
4. 経済活動の心理学
接客、購買意欲など経済活動に活かせる心の動きや、人の心を理解するためのアプローチを検討しています。
- 東京ディズニーリゾートはなぜ支持されるのか―パークの情景とおもてなしを通して考える-
- 幸せに働くことに関する心理学的検討
- 大学生のアルバイトにおけるバーンアウト
5. 社会状況の心理学
社会状況が心理面に及ぼす影響、社会状況における課題について検討しています。
- 新型コロナウイルスの流行前後のファン活動が心理に与える主観的幸福感について
- 新型コロナウイルスの流行が大学生にもたらした精神的影響
- ポジティブ心理学はどのようにして幸福感に影響を及ぼすのか―新型コロナウイルスに対して-
- COVID-19が与えた女子大学生の娯楽への影響
- コロナ渦におけるファン活動の変化
- 現代日本におけるいじめの現状と教育的支援の課題
6. 臨床心理学
深層心理や犯罪心理、心の不調という視点から、人間の心の不思議に迫ります。
- 女子大生の食生活とストレスの関連性
- 状況別対人不安-性格との関連-
- 家庭環境及び友人関係から検討する青年期の非行傾向行為
- Highly Sensitive Person (HSP:敏感な人)傾向が日常生活に及ぼすストレスの影響について-ストレスを軽減するためには-
令和2(2020)年度 卒業論文タイトル例
1. 自己意識の心理学
自分への意識や態度、性格など、自分のことだからこそ見えにくい心を探求しています。
- 幼少期の親子関係と現在の自尊感情、幸福感の関係
- 女子大学生における第二反抗期の経験と親からの自律援助が心理的自立に与える影響
- 女子大学生の体型意識
- 母娘関係が娘のアイデンティティ形成と精神的健康に与える影響について
- 顔面コンプレックスへの向き合い方と自意識の関連
2. 対人関係の心理学
家族関係、友人関係、恋愛と結婚など、人と共に生きる私たちの心を明らかにします。
- 女子大学生におけるファッションとアイデンティティの関係
- 女子大学生における親子関係と感受性について
- 女子大学生の友人関係における依存性の検討
- きょうだいの存在と性格特性との関係
- 出生順位とパーソナリティの関連
- 青年期における友人関係と本来感の気付き
- 女子大学生の劣等感と友人関係について
- 親友の定義
- カラーコンタクトが与える「かわいい」感情の違いについて
- 性格による不思議現象の影響
- 話し合いにおける大学生の言動について
3. 生活と文化の心理学
SNS、映画、小説、音楽、アニメなど、身近な生活と文化に表れる心の意味を分析しています。
- 女子大学生における化粧行動と化粧をする目的の関係
- 女子大学生の「ふつう」とは
- ダンスがもたらす心理的影響
- 女子大学生における心のゆとりとホスピタリティとの関係
- ファンをやめる時の構造について
- 女子大学生におけるハイヒールへの思考
- 幼年期における絵本の影響
- 女子大学生の痩身願望がダイエット行動に及ぼす影響についての研究
- 壁紙の色が人の感情に与える影響
- ファンとオタクの行動の違いについての検討
- ファン対象の写真を持ち歩く理由と効果
- 独り言のメリットについて
4. 経済活動の心理学
接客、購買意欲など経済活動に活かせる心の動きや、人の心を理解するためのアプローチを検討しています。
- ディズニーリゾートにおける気分調査
- 買い物とその人らしさについて
5. 臨床心理学
深層心理や犯罪心理、心の不調という視点から、人間の心の不思議に迫ります。
- 女子大学生の相談相手と幸福度の関係
- いじめ体験が身体的·精神的に及ぼす影響
- 女子大学生のストレスとコーピングの効果
- 女子大学生における歌唱時の不安と外向性の関連について
- 生活習慣と性格特性とストレスの関係
令和元(2019)年度 卒業論文タイトル例
1. 自己意識の心理学
自分への意識や態度、性格など、自分のことだからこそ見えにくい心を探求しています。
- 女子大学生の主観的自己と社会的自己のズレによる退陣不安の検討
- LGBT当事者を取り巻く問題の分析―多様性を認め合える社会を目指して―
- 食生活が抑うつに及ぼす影響
- 人のやる気やモチベーションを上昇させるには
- 卒論テーマはどのように決めるのか
- 女子大学生における睡眠が心身に与える影響
- 自己肯定感と変身願望の関連について
- かわいさについて~高身長の場合~
- 演奏状態不安と性格特性の関連性
- 青年期の自己形成と趣味の関連性について
2. 対人関係の心理学
家族関係、友人関係、恋愛と結婚など、人と共に生きる私たちの心を明らかにします。
- 女子大学生における恋人同士の束縛行動による恋愛関係の変化
- きょうだい位置による性格とソーシャルスキルの関係
- キャラの受け止め方と心理的適応の変化
- 同性の友人関係に対しての充実度
- SNSの利用と性格特性の関係
- 自分と異なる他者への捉え方
- 女子大学生における羞恥感情が援助行動に及ぼす影響
- 女子大学生における他者への寛容さと否定された経験との関係
- 女子大学生における優柔不断と出生順位との関連
- 友人関係の形成・維持過程と自己肯定感との関連
- 女子大学生における友人関係特徴とふれ合い恐怖的傾向と対人不安の関係について
- 恋人や好きだった人に対する依存と自己肯定感との関係
- 対人依存の経験の有無と対処法
3. 生活と文化の心理学
SNS、映画、小説、音楽、アニメなど、身近な生活と文化に表れる心の意味を分析しています。
- 「おおかみこどもの雨と雪」にみるアイデンティティ形成過程の違い
- ジャンケンの手を決める要因
- 復讐の心理~ハムレットから読み取る復讐がもたらすもの~
- 色彩が記憶学習に及ぼす影響
- 笑とWの印象の違いについて
- 女子大学生の読書離れの要因について
- アイドルファンとそうでない人の日常生活におけるコミュニケーションの取り方
- お笑いグランプリの分析による笑いがうつしだす時代背景
- 小劇場俳優の魅力
- メリーバッドエンドにおける視点の違い
- 女子大学生の人間関係形成における性の語りについて~SHIMONETA~
- 心を動かされた後の感情の変化~魔法少女まどか☆マギカより~
4. 経済活動の心理学
接客、購買意欲など経済活動に活かせる心の動きや、人の心を理解するためのアプローチを検討しています。
- 色と活動性の関係について
- アルバイト従業員のやる気と継続に関わる要因
- 大学生の一人行動に対する場所孤独感の感じやすさと自己肯定感の関係
- 女子大学生が「好き」を続ける理由
- ファッション販売での接客が消費者の購買意欲に及ぼす影響
- 女子大生における染髪意識
- 女子大学生における一人暮らし経験の有無による一人暮らしのイメージの違いとその要因
- 髪型が印象形成に与える影響について
- 女子大学生の飲酒行動と意識について
5. 臨床心理学
深層心理や犯罪心理、心の不調という視点から、人間の心の不思議に迫ります。
- 労働者のメンタルヘルスが労働意欲に及ぼす影響について
LICENSES AND QUALIFICATIONS
めざせる免許・資格
在学中にめざせる免許・資格をご紹介。
めざせる資格

※「任用資格」とは、特定の職種に勤めて有効となるものです。
心理学科でめざせる資格は、心理学に関する資格として「公認心理師※」「認定心理士」「ピアヘルパー」「准学校心理士」、人間の育ちにかかわる資格として「児童指導員(任用資格)」、その他の資格として「司書」「博物館学芸員」「社会福祉主事」があります。
「公認心理師」は、卒業に必要な科目のうち該当科目を履修して本学科を卒業した上で、複数年の実務経験、または大学院での2年間の養成課程を経ることで、受験資格を得ることができます。
「認定心理士」と「ピアヘルパー」は、卒業に必要な科目のうち該当科目を履修していくことで取得することができます。「ピアヘルパー」は、所定の3科目(「ピアヘルピング概論」「産業・組織心理学」「青年心理学」)を修得し、日本教育カウンセラー協会の筆記試験に合格することで、在学中でも取得可能です。
「准学校心理士」は、学校心理士に準ずる資格です。卒業後、各教育施設での実務経験と、学校心理士用の研修を受講することによって、通常より短い実務経験(3年間)を以て学校心理士を受験することができます。
心理学科では、公認心理師カリキュラムに対応する専門科目を開講しており、その一部の科目を履修して単位を取得した学生たちが、この准学校心理士のBタイプの資格を取得できます。
※「公認心理師」に関する科目について、本学での履修者数には制限がかかる場合があります。また、本学に心理学を学ぶ大学院はありませんが、「公認心理師」や「臨床心理士」をめざす学生のために、進学に向けて英語や専門科目に関する授業を開講しています。
進路

大学で心理学を学ぶことで想定される進路には、大きく3つあるといえます。1つめは、「心理学の専門職」になる進路です。この進路には、公務員の心理職(家庭裁判所調査官(補)、法務教官、児童心理司など)、カウンセラー、研究職・大学教員が想定されます。公務員の心理職は公務員試験に合格する必要がありますし、カウンセラー、研究職・大学教員として働こうとする場合には、大学院へ進学することが一般的です。
2つめは、「心理学で学んだことを活かして働く」という進路です。心理学で学ぶ心理測定や心理調査、心理統計の知識や技能を活かして調査会社に勤務する卒業生や、人とかかわることのできる仕事を志して児童指導員として福祉施設で働いている卒業生もいます。
3つめは、「働きながら心理学を活かす」という進路で、心理学科でもこの進路を選ぶ学生が最も多いです。一般企業での企画やマーケティング、営業・サービス業、さらには職場や家庭の人間関係など、心理学を学んだことが役に立つたくさんの場面があります。
このように、心理学科で学んだ心の理解や視点を活かすことのできる道は多様です。入学時には「やりたいことがわからない」「はっきりした目標がない」という学生も、4年間の学びのなかで少しずつ自分の道をみつけていきます。そのように迷いながら、模索しながら大学で学んでいく道のりを心理学科では大切にします。
QUESTIONS AND ANSWERS
学科Q&A
学科に関するよくあるご質問。
-
心理学科で学んだことは就職先でどのように役立ちますか?
-
心理学は社会のさまざまな場面で役に立つ学問です。心理の専門職に就かなくても、就職した後で役に立つ知識を学ぶことができます。職場での同僚、上司と部下の関係を含めた就労とメンタルヘルスやキャリア形成、また顧客への接客など人と人がかかわる場に心理学の知識は欠かせません。社会で活躍する人にとって心理学は身近でベーシックな学問です。
-
心理学の専門職以外には、どのような進路があるのでしょうか?
-
心理学の専門職以外にも、一般企業での企画やマーケティングそして人事、営業・サービス業、さらに職場や家庭の人間関係など、心理学で学んだことを活かすことができる進路はたくさんあります。児童指導員として福祉施設で働く卒業生、心理学的な測定、調査、統計の技能を活かして調査会社に勤務する卒業生もいます。 入学時には「やりたいことがわからない」、「はっきりした目標がない」という学生も、4年間の学びのなかで少しずつ自分の進んでいく道を見つけていきます。そのように模索しながら大学で学んでいくことを心理学科では大切にしています。
-
卒業後、スクールカウンセラーの仕事に就くことはできますか?
-
スクールカウンセラーとは、教育機関において、児童・生徒の発達を支援するための心理相談業務を行う専門家です。公認心理師もしくは臨床心理士の資格を取得すると採用されやすいでしょう。公認心理師は、大学で必要な科目(25科目以上)の単位を修得し、卒業後に2年以上の実務経験、または大学院での2年間の養成課程を経て、国家試験に合格してから登録を行うことにより、資格を得ることができます。臨床心理士は、大学で学んだ上で他大学の臨床心理士指定大学院に進学し、認定試験に合格して、資格を取得できます。
-
心理学の授業では、数学はどのくらい使いますか?
-
心理学では、実験や調査などを行って根拠となるデータ(資料)を収集して、必要な情報を導き出すために、心理統計法を使います。心理統計法を学ぶ上では、数学的な知識が必要となります。データ(資料)に基づいている心理学の科目全般にわたって、心理統計法の知識は非常に重要ではありますが、一人ひとり、教員が丁寧に指導しますので数字の苦手な方もご安心ください。