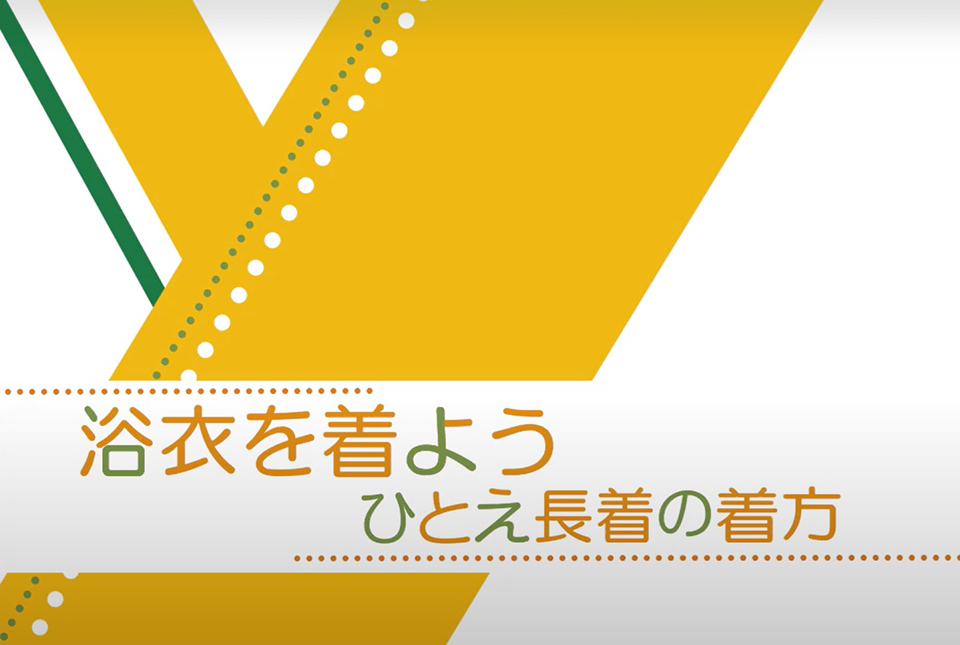トピックス
衣生活と家庭科教育について研究している柴田優子准教授からのメッセージを紹介します
柴田優子准教授は、衣生活を基本とし、衣生活全般における様々な課題についての研究や、それらについて中学生・高校生が「気づく」「考える」ことのできる家庭科の授業実践の研究をしています。
小・中・高の家庭科教育において、「衣」の学びとして思い出されるのは、被服製作実習だと思います。それが楽しかった人もいれば、中には苦手で嫌だった人もいるでしょう。でも皆さんは苦手と断言するほど、被服製作をした経験があるのでしょうか? 大学では「基礎被服構成学実習」(2年次・選択科目)、「被服構成学実習Ⅰ」(2年次・必修科目)、「被服構成学実習Ⅱ」(3年次・選択科目)と、3つの被服製作実習があり、布小物、洋服、和服の製作をします。適切な指導の下での実習では、誰もが最後まで作り上げることができ、「作るのが楽しい!」「使う(着る)のが嬉しい!」という気持ちまでを体験できます。その結果、卒業する頃には「手芸が趣味」となってくれる学生たちも、たくさんいます。

【写真】「基礎被服構成学実習」で、授業初日に「被服実習は苦手!」と言っていた学生が製作した作品たち

【写真】刺繍もできるようになります。製作後、ペンケースとして使用している学生が大勢います!

【写真】「被服構成学実習Ⅰ」で製作したパジャマを着装。長袖・長ズボンだけでなく、半袖や半ズボンの学生もいます

【写真】「被服構成学実習Ⅱ」で製作した浴衣を着装する様子。作るだけでなく、着付け方、畳み方まで学びます
家政福祉学科では、衣分野の専任教員の柴田准教授の下、衣生活の学びは製作だけではなく、被服材料、被服の手入れ、被服心理、衣生活の文化、持続可能な衣生活など多岐にわたります。家政福祉学科の必修科目の「衣生活論」(1年次・必修科目)から始まり、「被服構成学」(2年次・選択科目)や「ユニバーサルファッション」(3年次・選択科目)と分野が広がっていきます。また、柴田准教授は家庭科教育の指導も担当しており、「家庭科教育論Ⅰ」(2年次・教職必修科目)、「家庭科教育論Ⅱ」(2年次・教職必修科目) 、「家庭科教育法Ⅰ」(3年次・教職必修科目)、「家庭科教育論Ⅱ」(2年次・教職必修科目)、「家庭科教育演習」(3年次・教職選択科目)と積み上げながら、中学生・高校生が「気づく」「考える」ことのできる家庭科の授業実践ができる家庭科教員養成のための授業を展開しています。
柴田ゼミ(衣生活・家庭科教育)では「衣生活または被服教育」をテーマとして、生徒の主体的な学びにつながる衣生活教育の教材づくりをめざした研究などを行っています。
浴衣の着衣でつまずきやすい「おはしょり」の処理について、製作したシースルー生地の浴衣を使って、わかりやすく説明した動画を、ゼミの学生が卒業研究として作成しました。この動画は、浴衣の貸し出しをおこなっている千葉県内の中学校・高等学校や、家庭科教員になった卒業生などに共有し、授業の一環として活用してもらっています。
【写真】ゼミの学生が卒業研究として作成した動画のタイトル(クリックすると別ウィンドウでYouTubeが開きます)
家政福祉学科では、家庭科教諭、社会福祉士、保育士の取得をめざす学生たちを応援しています。
家政福祉学科 家政福祉コースの学びはこちらから
家政福祉学科 児童福祉コースの学びはこちらから
家政福祉学科の紹介動画を公開中! 動画はこちらから
【オープンキャンパス・イベント情報】
8月27日(火)・28日(水)、「総合型選抜 書類作成講座」:申込はこちらから
9月22日(日祝)、「秋のオープンキャンパス」:申込はこちらから
入試相談・学校見学は随時受付中です!
詳細はこちらから