トピックス
乳幼児の絵本の読み聞かせについて研究している星野美穂子助教からのメッセージを紹介します
星野美穂子助教は乳幼児の絵本の読み聞かせについて研究しています。
本をたくさん読む子どもは、知的能力が高いということを聞いたことがあるのではないでしょうか。また、本をたくさん読む子どもは情緒的にも安定していることがわかっています。赤ちゃんの時期から、たくさんの絵本を読んであげたいですね。
私の研究は簡単に言うと、以下の2点です。
①どんな絵本を選ぶとよいのか
②どんな読み方がよいのか
実は、「大人が子どもに読んであげたい絵本」と、「子どもが好きな絵本」にはギャップがあることが多いのです。子どもに絵本を読んであげても、ちっとも集中してみてくれない……と思った方もいるのではないでしょうか。保育士の経験やパパ・ママの勘ではなく、様々な絵本を実際に子どもに読み聞かせてみて、その反応を観察し、記録をとり、点数化していきます。また、保育園や幼稚園で子どもが実際に手に取って見ている絵本、読んでほしいとせがむ絵本を記録し、リストにして「子どもが選ぶ絵本リストの作成」をめざしています。子どもが大好きな絵本を少しだけ紹介しましょう。
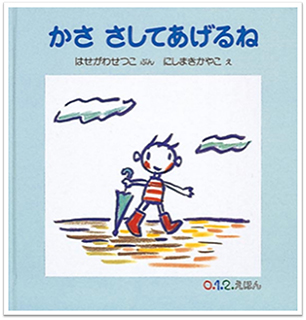
『かさ さしてあげるね』
はせがわせつこ 文
にしまきかやこ 絵
福音館書店
*雨降りが楽しくなる赤ちゃん絵本です。
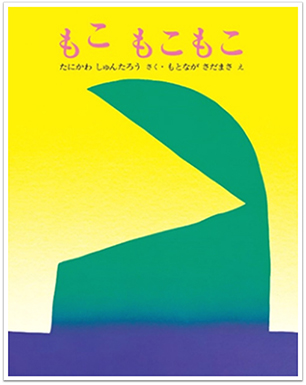
『もこもこもこ』
たにかわしゅんたろう 作
もとながさだまさ 絵
文献出版
*赤ちゃんが大笑い、オノマトペが楽しめます。

『くっついた』
三浦太郎 作
こぐま社
*思わずにっこり。ママとくっつきたくなる赤ちゃん絵本です。
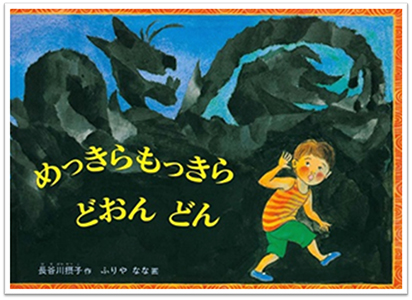
『めっきらもっきらどおんどん』
長谷川摂子 作
ふりやなな 画
福音館書店
*3歳から楽しめます。絶対にはずさない絵本です。

『おばけのコックさん』
西平あかね 作
福音館書店
*拾い読みも楽しめる絵本です。小学生にも大人気の絵本です。
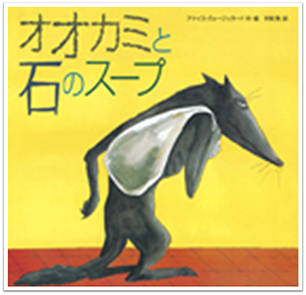
『オオカミと石のスープ』
アナイス・ヴォージュラード 作
平岡敦 訳
徳間書店
*4、5歳から。小学生も楽しめる絵本です。
また、読み聞かせの方法にも工夫が必要です。ベテランの保育士は子どもの反応をよく見て絵本を読み進めていきます。この手法を獲得するために演習授業では読み聞かせの練習をしています。学生の読み聞かせをルーブリック形式で、聞き手の学生が評価していきます。他者の読み聞かせを見たり、自分の読み聞かせを客観的に評価されることを通して自己洞察を促し、数回の練習で読み聞かせ技術を効果的に向上させていくことができるのです。
そして、その成果を発揮する場として、家政福祉学科の児童福祉コースでは「あそぼう・はなそう会※」を実施しています。授業で学んだことを、地域子育て支援の場として、未就学児とその保護者の方を対象に楽しい遊びの場を提供し、その中で絵本の読み聞かせも行います。通常は子どもと保護者のみ来場可となっていますが、里見祭(大学祭)では一般の方の来場も可能ですので、ぜひ、遊びに来てくださいね。
※2022年7月より定期的に開催している、児童福祉コース主催の「あそぼう・はなそう会」。毎回テーマを決めて、地域の親子(未就学児と保護者)を和洋女子大学に招き、児童福祉コースの教室であるプレイルームで、にぎやかに開催しています



