トピックス
「心理学の『メガネ』を通せば、世界の見え方が変わるはずです」(田中佑樹助教)
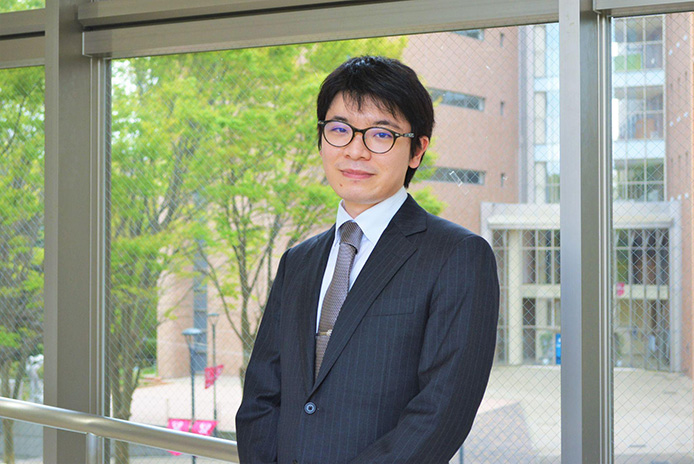
■専門・研究分野
専門分野は臨床心理学、健康心理学で、「認知行動療法」という心理療法のアプローチに基づいて、依存症を抱える方の行動変容や健康な方のストレスマネジメントのための研究に取り組んでいます。これまでの最も中心的な研究テーマは「ギャンブル障害(いわゆるギャンブル依存症)」で、ギャンブルが続いてしまうメカニズムの個人差に着目して、その差異に応じた効果的な支援方法の構築を目指した検討をしてきました。また、公認心理師、臨床心理士としての活動も続けており、医療機関において患者さんに対する認知行動療法を用いた心理的支援に携わっています。
■心理学を学んでいてよかった、と思えたエピソードはありますか?
私は普段からメガネをかけているのですが、メガネをかけることによって見えにくかったものがよく見えるなど、世界の見え方が変わります。比喩的な表現になりますが、心理学(認知行動療法)的な思考法は私にとって「メガネ」のようなものであり、世界の見え方を大きく変えてくれたものだと思っています。
心理学を学ぶ以前は、「気持ちが変わらないと行動は変えられない」と思っていました。たとえば、友達とのトラブルなどの嫌なことが起こったときには、嫌な気持ちが収まらないと自分の好きなことをしても楽しむことができない、と考えていたのです。しかし、認知行動療法の発想は真逆で、「行動を変えれば気持ちも変わる」と理解します。先ほどの例でいえば、友達とのトラブルなどで嫌な気持ちが生じたときには、むしろ他の楽しいことをすることによって、結果的に嫌な気持ちは減らすことができるかもしれない、と考えるのです。こうした認知行動療法の発想は、心理学の初学者だった頃の私にとっては目から鱗で、それ以来、徐々にですが、日々に活かすように心掛けてきました。最近では、落ち込むようなことがあったときには、いつもよりもちょっと高い美味しいものを食べたり、欲しかったものを買いに行ったりして、気分を変えて次にまた頑張るための活力を養うようにしています。
■和洋女子大学で働き始めて早3年。助手から助教になり、心境や意識など変化はありましたか?
昨年度までは、助手として学生たちを裏で支えるような役割でしたが、助教に昇任した今年度からは、授業などで表立って学生たちとかかわることが多くなり、責任の大きさを痛感しています。まだ新米教員ですので、講義や実習、ゼミなど、幅広い科目を担当する中で、その時々の役割を果たせるように試行錯誤しています。たとえば、国家資格である公認心理師に対応した専門性の高い科目では、自分自身の公認心理師としての経験を活用しながら、具体的な実践のイメージを持ってもらえるように工夫しようと試みています。
一方で、心理学科以外の学科の学生も多く受講する共通総合科目では、心の健康を保つ上でも役立つ心理学の理論や技法を楽しく学んでもらい、より良い大学生活を送るためのサポートになればと取り組んでいます。
■趣味や、今、ハマっていることがあれば教えてください
音楽が好きで、高校時代にオーケストラ部に所属していた経験から、クラシック音楽をよく聴きます。最近、高校生の時に使っていた音楽プレーヤーが発掘され、10年以上も前のものですが、まだしっかり再生することができました。早速、その音楽プレーヤーを研究室に持ち込み、集中して作業したいときに、高校時代によく聴いていたお気に入りの曲を聴いています。中でも、モーリス・ラヴェルというフランスの作曲家の音楽が大好きで、シャルル・デュトワ指揮による「亡き王女のためのパヴァーヌ」、「スペイン狂詩曲」、「左手のためのピアノ協奏曲」……といった曲は、心理学が学べる志望校をめざしていた大学受験の時期によく聴いていたのでした。その色彩的で洗練された音の中に、高校時代の想い出も微かに呼び起こされつつ、学内外でいただいている仕事に励む活力をもらっています。
■学生たちへのメッセージ
心理学科での学びには、実生活に活かしていける要素が散りばめられていると思います。そうした、1つひとつを「パーツ」として集めて、4年間かけて自分なりの「メガネ」をつくっていってほしいと願っています。そのためには、毎回の授業で学んだことについて、自分の日常生活とどのような接点があるのか、あるいは実際にどのように活用していくことができるのかなどを考える癖をつけてもらえるといいのではないかと思います。そして、分からないことや困ったことがあったときには、ぜひ積極的に教員に質問や相談をしてみてください。そうしてできた「メガネ」を通せば、きっと世界の見え方が変わり、人生が豊かになるはずです。私も和洋女子大学の一教員として、みなさんの「メガネづくり」をサポートしたいと思っています。
心理学科の学びについてはこちらから
田中助教の助手時代のインタビュー記事はこちらから
