AI技術系
情報技術を基礎から
丁寧にしっかり学ぶ




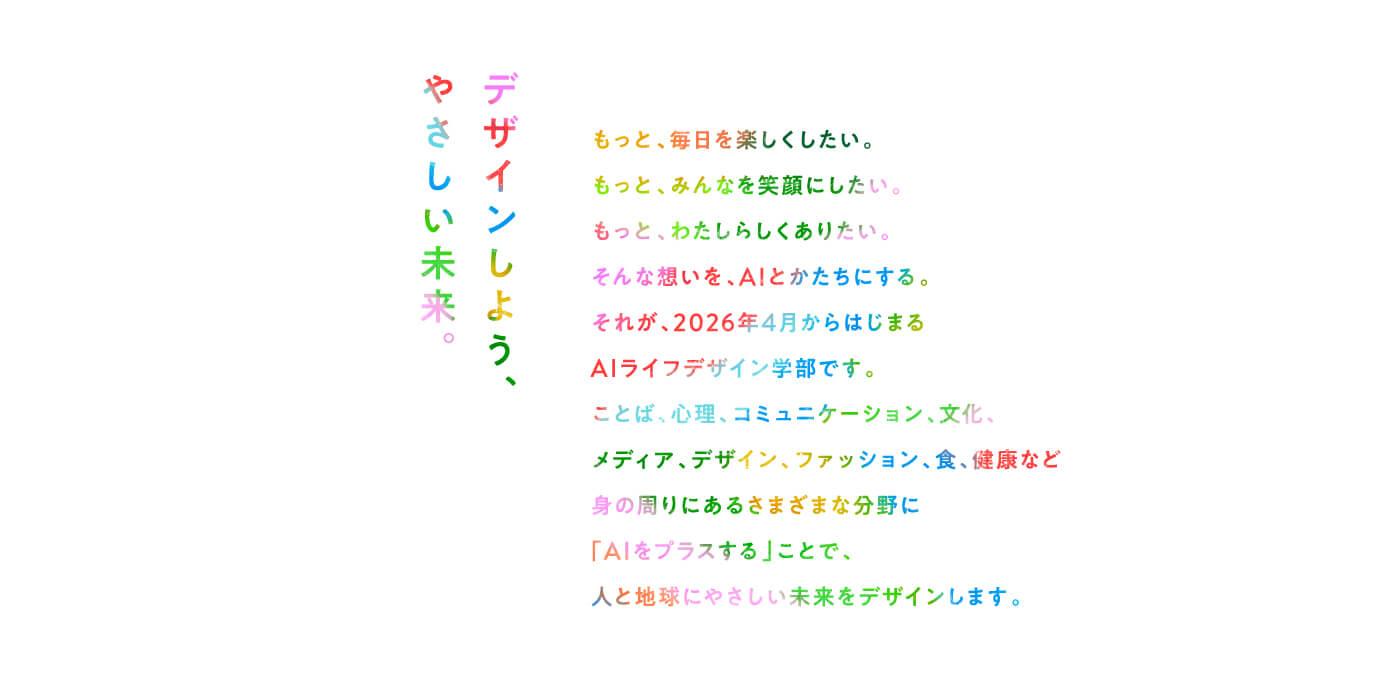
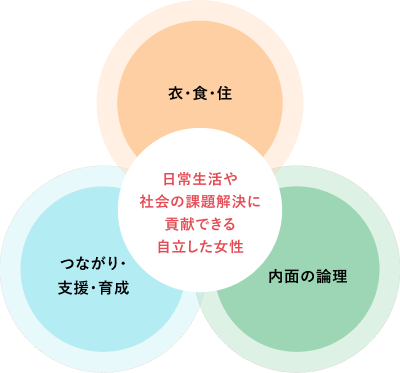
既存学科の学びを
情報技術を基礎から
丁寧にしっかり学ぶ

和洋女子大学が
育んだ学問を

身につけた知識と
問題を解決する
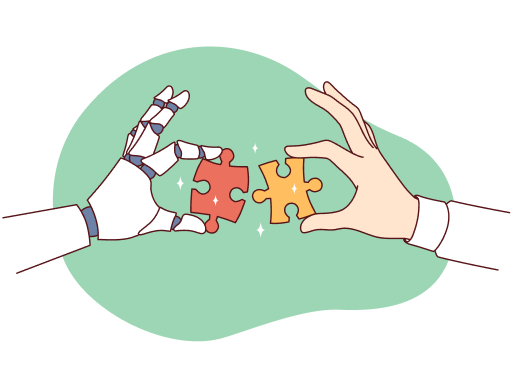


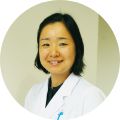










メールマガジンの配信をご希望の方は、